石田三成の項目の更新が遅くなってます💦ようやく手を付けました。
三成の足跡をたどっていきます。本能寺の変、そして秀吉天下取りに向けての道のりを三成も歩みます。
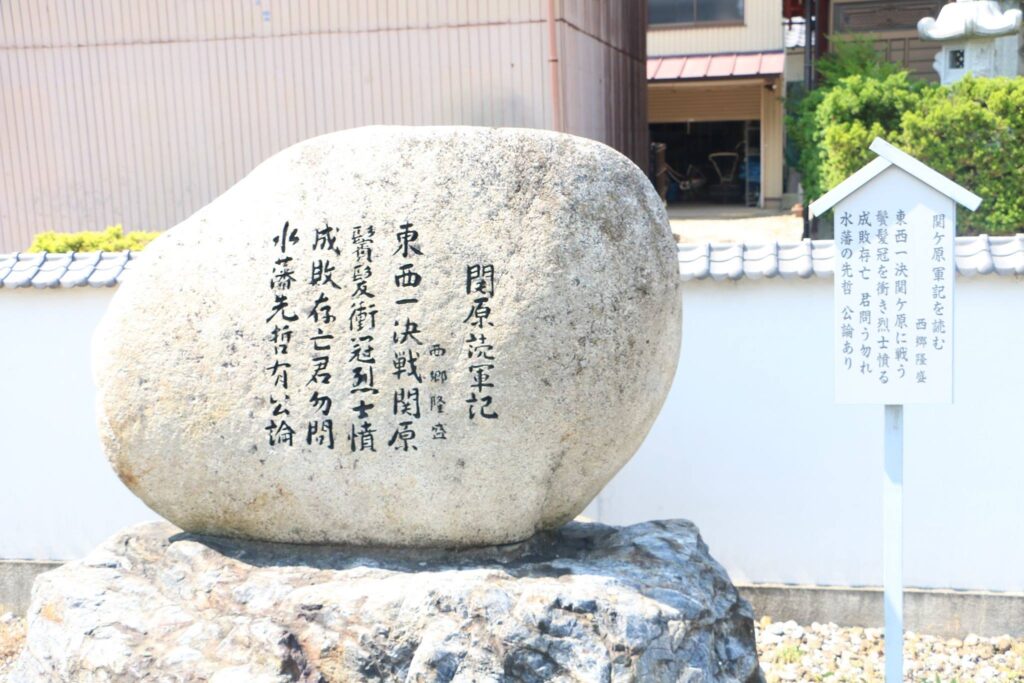
秀吉に仕える
三成が秀吉に召し出されたのは、天正2年(1574年)の15歳の頃であったと考えられます。近習として仕え、秀吉が織田家の宿将として各地に転戦される際には、三成も従い、忠勤を尽くしたことでしょう。彼が持っていた生来の才気と、精励恪勤の姿勢が、秀吉の信任を得たことは、容易に想像できることです。
「名称言行禄」には、「三成、美少年して秀吉の寵を得たり」と記されており、「石田軍記」には「即ち召して夜閨を共にし、玉枕を並べさせ給ひ」との記述もあります。しかしながら、「石田軍記」は三成を徹底的に姦物として描こうとしたものであり、「名将言行禄」の記事もこれに基づいていると思われますので、根拠のない誤った説と考えられます。秀吉は女性に対しては相当な情熱を持っていましたが、男色の趣味はなかったとされています。したがって、三成が寵愛された理由には、他にもっと適切な背景があったのでしょう。
三成が18歳の天正5年(1577年)、秀吉の中国征伐に従って播磨に下った際、三成は伝奏の役を命じられました。秀吉の活躍が華々しかった当時、三成もその働きにやりがいを感じていたことでしょう。三成が元服をいつ済ませたのかは定かではありませんが、おそらく中国地方での転戦中に行われたのではないかと考えられます。「近古史談」によれば、その頃、三成は元服の祝いとして秀吉から2千石の加増を内示されたそうです。しかし、三成はこれを辞退し、その分で大谷吉継を召し抱えるようにと、強く推薦したとのことです。
元服の祝いとして、当時の三成に2千石は過分であったため、この話が正確かどうかは疑問です。しかし、三成には人に対して好き嫌いが激しい一面があり、特に好ましい人物には非常に深い情を注ぐ性格であったことは確かです。三成と吉継が生涯にわたって深い友誼を築いたことは事実であり、したがって、このような逸話を一概に否定することもできません。
秀吉に信頼されていく三成
秀吉は中国征伐の功績により、従来の近江二郡に加えて、但馬や播磨などを信長から賜りました。そこで、家臣たちの功績を称え、それぞれに加増を行いました。三成にも500石の加増が内示されましたが、三成はこれを辞退し、代わりに宇治川・淀川の岸に生えるヨシや葦などの運上(課税権)を請け負いました。これらのヨシや葦は、これまで沿岸の住民が自由に刈り取って、屋根を葺いたり簾を作ったりして利用していたものでした。三成はこれに課税することで、秀吉に1万石相当の軍役を負担することを約束しました。
その後、秀吉が丹波の波多野氏を攻めた際、三成は団扇九曜に金の吹き流しをつけた旗を先頭に立て、金の吹貫の腰印をつけた数百騎を引き連れて参陣しました。運上銭でこれほどの仕度を整え、見事に約束を果たした三成は、大いに秀吉の感賞に浴したと伝えられています。
この話は「古今武家盛衰記」や「名将言行録」などに記されており、三成の出世のきっかけとして語られています。しかし、秀吉の波多野攻めが天正8年(1580年)頃であったとすると、当時の秀吉には宇治や淀を支配する力がなかったため、矛盾が生じます。もしこの話が事実であれば、それは天正11年頃(1583年)のことであり、波多野氏攻めは関係がなくなります(波多野氏はすでに明智光秀によって滅ぼされています)。いずれにせよ、このような逸話が伝わっているということは、三成の経済的な才覚が非常に優れており、それが秀吉の信頼を勝ち取る一因となったことは推測できます。
二度の「天下分け目」を経て
秀吉は天正10年6月の本能寺の変を奇貨として、明智光秀を討ち、その迅速な行動により、織田家中で比類なき地位を確立しました。これに立ちはだかったのが柴田勝家で、天正11年4月、両者は近江賤ヶ岳で対戦しました。勝家が柳ヶ瀬に出陣すると、三成は浅井郡の称名寺の僧侶たちを使って、柳ヶ瀬の動向を探らせ、秀吉に漏れなく報告しました。
また、勝家の宿将・佐久間盛政が賤ヶ岳の北麓を経て、大岩山や岩崎山の砦を奪うと、秀吉は大垣にいた際、1万5千の兵を率いて、電撃的に反転しました。この時、三成は先発を命じられ、沿道の村々に触れて、松明を準備させました。そのおかげで秀吉の本隊は行動に支障をきたすことなく進軍でき、この松明の明かりは佐久間隊にとって、大軍が迫っているかのように見え、兵士たちの肝を冷やしました。佐久間隊が驚いて撤退を始めると、秀吉は旗本に命じて、退却を追撃させました。いわゆる「七本槍」が活躍したのは、この時の追撃戦でのことです。七本槍の武功を立てたのは、福島正則、加藤清正、加藤嘉明、脇坂安治、平野長泰、片桐且元、糟屋武則の七名です。しかし、「一柳家記」によると、この時最初に槍を挙げた者は「先懸衆」と呼ばれ、その中には一柳直盛、大谷吉継、石田三成が含まれていたと伝えられています。三成は後世、文官として軽視されがちですが、24歳のこの時、白兵戦に参加し、抜群の武功を立てたという点は注目に値します。
秀吉にとって賤ヶ岳の戦いは、事実上の天下分け目でありました。秀吉はその余勢を駆って北国を制圧しようと、書状を越後の上杉景勝に送り、同盟を申し入れました。景勝は家臣の直江兼続と謀り、使者を送って秀吉に戦勝を賀し、秀吉の帷幕である石田三成や増田長盛に、それぞれ馬1匹、白布50端を贈って会釈しました。以後、秀吉と景勝との交渉はすべて三成と兼続との間で行われたため、両者の関係は年々深まり、最期まで変わることはなかったと言われています。

※※※ このサイトは、アフェリエイト広告を掲載しております ※※※


 | ブログをライフワークにしてお金と自由を生み出す方法 [ 中道 あん ] 価格:1705円 |



コメント